 トップ・
スケジュール・
エッセイ・
プロフィール・
CDアルバム・
ブログ
トップ・
スケジュール・
エッセイ・
プロフィール・
CDアルバム・
ブログ
|
| 2008・ 2007・ 2006・ 2005・ 2004・ 2003・ 2002・ 2001・ 2000・ 1999・ 1998 |
|
竹下ユキ エッセイ1999 1999年2月 ジァンジァンという小屋のこと。 1999年3月 ジァンジァン後始末記 1999年4月 熱血!咽喉科先生!! 1999年5月 パリ祭の季節に思う 1999年6月 続・パリ祭の季節に思う 1999年8月 観客談義 1999年9月 続・観客談義 1999年10月 観客談義・最終回 1999年11月 職業は。 最新エッセイ |
1999年2月 ジァンジァンという小屋のこと。 思えば色んな場所で歌ってさたものだ。10人も入れば−杯になってしまうような飲み屋から、国際フォ−ラムみたいな心の通わないホール、やみくもに人だらけの野外ステージ、お役所の匂いのする公共の施設などなど.運ばれて行くだけの会場には思い出もないので、記憶も残らない。ところが一回行っただけなのにいつまでも心に残るそんな場所もある。わかりやすく言うと「コンサートホール」と「小屋」の違いなのである。私がどちらを好むかと言えばもちろん「小屋」である。「小屋」と言うからには、あまり大きくてはいけない。そしてあまり綺麗でもいけない。何か自分のことを言っているようで少し照れるが(照れてるようではいけないのである。)。 だいたい何でもそうだが、公が予算をふんだんにかけて作ったものより、個人の思い込みで作り上げたものの方が味わい深い。かつてもそういった小屋が栄えては消えていった。私が出演した限りでは例のシャンソン喫茶『銀巴里』や『赤坂クリスタルルーム』というレヴューショーを見せるレストランシアターなどがあった。そして渋谷にある『ジァンジァン』という小屋も来たる2000年をもってしていよいよ閉館するのである。個人が作ったものだから個人の勝手でやめたりもできるわけだが、歴史が続けば続くほど個人の粋を超えてて無数の人々の思い入れが強くなる。単なる「スペース」が「小屋」になるのはその頃だ。劇場に魂が宿るというのは本当のことなのである。 しかし、私がかつて出たことのあるこういった小屋は例外なくどれもおどろおどろしい。それはどういうわけか何処も美輪明宏さんや戸川昌子さんか出ていたということと関係が無くはない。(分類:おばけ屋敷)あるいはシャンソンというジャンルの出しものそのものが、かなり特殊なものだからなのかもしれない。シャンソンと言えば「ろくでなし」だの「サントワマミー」だのを思う人もいるかもしれないがそれは全く間違いである。そういうものはシャンソンとは言わない。「シャンソン歌謡」である。シャンソンというものは少なくとも男と女が居たならば、そこには必ず別れがあり、裏切りがあり、恨みがあり、狂気があり、仕舞いには殺しまであるものなのだ。清らかな娘はとんでもない男に騙されて、果ては娼婦になるのが正しいシャンソンのあり方である。おまけに自分の人生を語るわ語る。理屈はこねる。呑気な顔して一生を過ごすなんてとんでもない話なんである。私がシャンソンに辟易したのも実はこうした「人生の重さの押し売り」であったのだが、それも表現者の力量による。美輪さんなどはその重さすらも芸に高めていった天才であるのであれだけ人を感動させることができる。私のように呑気に暮らしている者の説得力は薄い。 とは言え、私もジァンジァンには長いこと出た。人生の重さは説けないので次第にシャンソンを歌うことはなくなったが、強いて言えば呑気に生さる楽しさみたいなものは表現したい。絶望なんかしたくないのである。そこでこのところのテーマは『病は気から』。アホらしいこともたくさんやったしアホなゲストも出た。(ごめんごめん。五十畑君。)でもジァンジァンでできたくらいだから多少はおどろおどろしかったのかもしれない。いずれにしてもジァンジァンでやったことはジァンジァンでしかできない一回制のものである。魂の宿った小屋にはそういうパワーがある。それをいいことにジァンジァンのスタッフのお愛想が無いのも有名だが、これも一種の“格好付け”なので気にすることではない。電話の応対と受付での応対はそっけないらしいが、いったん慣れると、よく働く気持ちのいい若者ばかりである。彼らも夢から覚めて新しい道を探して行くんだろう。 かつてこの小屋から色んなスターが出たり、あるいは逆にスターが出たがったりしたそうである。私はこの小屋からスターになることはでさなかったが、流れ星くらいにはなれたかもしれない。これからも流れていくんである。一生の間にこういう場所との出会いがあったことは掛け替えの無い幸せというものだ。 さて、2回公演できるのはこれで最後。2月28日のジァンジァンには万障お繰り合わせの上、おでかけくださいな。(おまけに私はその前日に歳を取る。いやですねえ。) 1999年3月 ジァンジァン後始末記 先月のジァンジァンには実にたくさんの人が来てくれた。この小屋がじき無くなるということが大いに影響したのである。当然様々な人々がそこには居た。突然ステージに上がってきて歌った人もいた。初めてのことだった。それも女装のオジサンだった。「ユキちゃんは色々な知り合いがいるんだね。」と後でバンドの人達は言ったが、誓って言うがあの人は私の知り合いではない。たぶん私の知り合いの知り合いだろう。(大して変わりはないか。)ま、こんな仕事をしている都合上(どんな都合か?)酔っ払ってオ力マバーヘ繰り出したことが無いとは言えない。(つまり、ある。)しかし、あの人は私の知り合いではない。がいずれにしてもあの人は悪いかんじではなかった。ステージを実によく楽しみ、盛り上げていた。喜ばれると調子に乗るのが芸人の浅ましさである。私は時々歌手であることをすっかり忘れ、ほとんどバラエティ状態になる。これが私がいつまでも出世しない原因のひとつであることは重々わかっているのだが、歌よりしゃべることに情熱を燃やしたりする。ライヴが終わると「あの話が面白かった」とか歌と関係ないことに感激して帰る人が多々いる。もちろんつまらないより面白い方がいいに決まっているのだが、もしこれで話が乗らなかったらどうなってしまうんだろ、と想像すると背筋が寒くなる。しかし、いつも寒くなった背筋が温まると、このことは忘れてしまう。 ところが、今回は忘れることができない羽目になったのである。コンサートが終わると必ずお客さんにアンケートをお願いするのだが、たいがいは負けじとぱかりアホなことを書いてきたり、よかったの楽しかったの無難な意見が多い。しかし今回のお客さんは手強かった。無記名なのでどんな人かは皆目わからないが、初めて私のライヴに来たとある。読解不可能なくらいゴチャゴチャと汚い字でしがも強烈にテゴワイ。『下手でなく、トーワもうまく楽しかった。が、何を歌っても同じように思われるし、何が歌いたいのがわからない。どれを取っても引きつけるものがない。(以下営業妨害になりかねないので省略。)』う〜ん.何者じゃ!!是非会ってみたい人物である。お会いした際には「おっしゃる通りでございます。」と言ってしまいそうだが、言わないように気をつけよう。一応歌うことで生きているのだからである。せめて「あなたも一日も早く竹下のライヴに慣れてください。」とお願いしよう。また来てくれることを心から祈るけれど、無理だろうなあ。 ひとつのコンサートが終わると平気で2キロは痩せる。□は大きいが気は小さいのである。ところが一日もたつと平気で2キロは太る。結局何もなかったことになる。こうして再び反省の無い毎日が始まるのだ。しかし今回のジァンジァンで確がな手応えもあった。新しく作ったオリジナル、題して『老人力3部作。” ぼけたい〜Hagellunah(ハゲルナ)〜寝たきりマンボ”』は作曲にも積極的に関わったこともあって大変自信が持てた。これかな、私の生きる道は?と思えるような手応えである。実はこんなこともあろうと、このところ密かにピアノを習っているのである。実に25年ぶりのことだ。さすがに指は動かず、理論は覚えられずで老人力を身に付けている最中だが、ながなが面白く久々の趣味となった。いい作品を書きたい・・・・。いくつになっても夢は捨てられない。 ちなみに今年もう一回ジァンジァンでライヴができることになった。私のイカサマを指摘する人がいると同時に私のイカサマが好きな人もいるのである。〔9月25日(土)の2:00〜の1回ステージ]これが正真正銘最後のジァンジァンである。いい作品(?)を引っ提げて心に残るライヴをしたいものである。 1999年4月 熱血!咽喉科先生!! 願わくば医者通いなどしたくない。と、誰しもそう思う。特に歯医者であるとか、骨折後のリハビリであるとか、野蛮な痛みを伴うものは避けたい。そして耳鼻咽喉科へ行くのもあまり気持ちのいいものではない。耳や鼻はまだしも、歌を歌うわけでもないのに人前で大口を開けて喉の奥まで点検され、挙げ句の果てにこっちの都合などおかまいなしに、気持ちの悪い薬をぐいぐい塗りたくったりする。まったく人間のやることとは思えない。 ところが困ったことに職業柄この『咽喉科』とは切っても切れない間柄なのである。『インコウカ』というネーミング自体が何やら品の無さを露呈しているが、そこと関係が深いのである。情けない。なぜならしばしば私は音声障書を起こす。つまり声の出が悪くなる。自分の体より大きな歌を歌おうとするので声帯がオーバーヒートするのである。黙っていればすぐ治るが黙っていると仕事にならないので頼みの綱で咽喉科へ駆け込む。たいがいがお爺さん先生で動作が極めておっとりしている。ゆっくり薬を塗る。時々的を外す。もう一度やり直す。気持ち悪さが倍増する。発狂しそうになる。が、インコウカなんてこんなもんだと諦めていた。 そのうち、我々のような職業の者はかかりつけのインコウカ医を決めていることを知った。都内には歌手や役者が患者の中心という医院が数件あって歌手や役者より有名な医者もいる。この人たちのいいところは一カ月かけてゆっくり治療しましょうなどという呑気なことを思わない点だ。オーディションだ、コンサートだ、舞台だと、今日出なければならない声は今日出させる。当然劇薬も使う。(ぼやぼや薬なんて塗らない。喉に直接注射だ。)極端な話、明日のことはまた明日考えようという発想だ。渋谷の某先生はとにかく芸能人(有名なほどよろしい)好きである。かつて医院を訪れたことのある有名人の名前が所狭しと書いてある。時には「君は本当にやる気があるのかっ!!」などと若い役者を叱咤していることもある。ただし宝塚の人達には妙に優しいらしい。この医院の壁に名前が載ったら自分も有名になったと思って間違いない。練馬の某先生は音楽の好みがはっきりしていて、ロック少年に「そんな堕落した音楽をやっているから、こういう喉になるのだ。」などと言い、妙なベルカントで自分のバリトンを聞かせたりするらしい。みんな個性的だ。熱血だ。うかうかしていられない。そして私も色々な医院へ行ってみたが、現在イチオシは日比谷の東京商工会議所の中の診療所である。子供の頃NHK児童合唱団にいた友人に勧められたのだが、この先生はそこの主治医だったそうである。今は息子が受け継いでいるが、彼もこの合唱団で歌っていたというのだからインコウカとして不足はない。おまけにここは穴場なので待ち時間が少ない。ところが流石最近は口コミで歌手や役者が訪れるようになった。つまり、この先生も熱血咽喉医師だったのである。とりあえず彼をインコウカ・ザ・ヒーローと呼んでおこう。 ヒーローは30才くらいだろうか、小柄で童顔丸顔、団子三兄弟のひとり(どれも同じか)に似ている。彼の特色は診療所を超えた治療にあるだろう。東に本番前に声の出ない投者が居れば診察時間の終えた後に楽屋まで往珍し、西にコンサートを控えた歌手が居れば休日返上で診療所を開ける。事実私も日曜日にコンサート予定があるのに前日の土曜日まで芳しくないことがあった。するとヒ一ローは「まずいなあ、明日は友達の結婚式の予定を入れちゃった」まずくなんかない。明日は日曜だ。あんたは結婚式に行く権利がある。「いや、何とかなるな。お昼頃新宿駅に来られますか?」行ってどうする?「注射ぐらいなら打てるでしょう。」新宿駅で注射?どこで打つんだ?どうやって打つんだ?私は咄嗟に、声は出るようになっても警察に捕まって結局コンサートに行かれない羽目になるような気がしてこの申し出は丁重にお断りした。 ヒーローは又、劇団の存続を救ったこともある。キャラメルボックスという人気劇団の役者が麻疹になった。こういう場合本来興業は中止される。客も含めて感染する危険性が高いからである。興業中止となれば何億という損害だ。しかし、発病確認何日以内ならば感染を防げると気づいたヒーローは日曜日だというのに無理矢理薬問屋を叩き起こし、ありったけのワクチンを入手、劇団員全員に予防接種をした。興業は無事成功。キヤラメルボックスからの表彰状が診察室に飾られているのは言うまでもない。 ヒーロ−は益々熱血度を増していくことだうう。白衣の下にチラリと見えるスーツがずいぶん高級なのを見るにつけ、育ちがいいのかそれとも、どんな大女優の楽屋にも馳せ参じられるよう準備しているのか、複雑な印象を受ける。彼の診察室に有名人の名前が並ぶ日も遠くはないだうう。あんまり突っ走り過ぎて危険な目に会わないよう祈りつつ・・・。 1999年5月 パリ祭の季節に思う 7月14日という日は私にとって大変シンボリックな日である。7月14日・・・その日はフランス革命記念日であって私の母国のお祭りなのである。(ウソウソ)。母国でないことは確かだが、フランス革命記念日であることは間違いない。これを『パリ祭』と呼ぶ。では何故そんな異国の記念日が私と関係があるのか?これを話すとあまりに長く悲しい(?)私の歌手生活の話になるのでやっぱり話そう。 日本という国は誠に変わったくにであると言わねばならない。アジアの極東にあるこの島国は意固地に孤立するどころかあらゆる国の文化習慣を受け入れ、消化し、何の違和感もなく元あるものと調和させてしまう。『パリ祭」という日本独自のイベントはいまから30数年前シャンソン歌手の石井好子様が始めた、日本人歌手たちがフランスの歌(つまりシャンソン)をほぼ例外なく日本語で歌う催しなのである。推測するに当時は日本人にとってフランスは「おフランス」だった。フランスは文化・ファッションの都、いわばインテリとフルジョワの象徴だった。そして世の中は戦後の復興から高度経済成長へ。何もかもが華華しい空気があった。テレビの普及と紅白歌合戦の時代だ。そんな中でパリ祭は生まれ育ちそして今でも華やかなイベントとして7月14日を中心に行なわれている。オペラ歌手、民謡歌手、演歌歌手、ジャズ歌手、その他ラテンだハワイアンだカントリーだと歌手にも色んなジャンル分けがされるが、その中で、日本人だが好んでフランスの歌を歌う歌手たちをシャンソン歌手といい、とりわけ強力な異彩を放っている。外国の作品を取り上げる場合、どんな国のものでもその国のイメージを強く押し出した場合(例えば日本人の顔だが、フラダンスしなから歌うとハワイアンとか、槍持って歌うとマサイ族とか。)やればやるほど民族物産展系のマニアックな展開になる。そんなわけでロシア民謡やラテン業界は人口が先細ったのだと思われる。ところがシャンソン業界だけは何故かしっかり現代日本社会に息づくことができた。確かに歌の中で「パリがどうした」とか「サンジェルマンデプレがどうした」とか「ジュテ−ム」やら「モナムール」やら言う日本語歌詞を聞くにつれ「そんなもん食ったことねえだ。」と思ってしまうこともしばしばだが、日本のミュージカルが日本人の顔してメアリーだ、フランソワだと呼びあう不思議さを通り越して客席を魅了してきたのと同じようにひとつの芸のジャンルとして確立してきた。その上カルチャ−センターブームに起を得て「誰でも歌えるお洒落な洋楽」のイメージも定着した。以前も書いたが、『シャンソン歌謡」の誕生である。単にその時代の流行りもので終わらなかったところがシャンソン業界のフレキシブルなところである。 そして皆様のよく知っている竹下ユキというシンガーも分類としてはシャンソン歌手ということになっている。何を隠そう、この私こそが今を去ること10年前のシャンソンコンクールで優勝するという快挙を遂げた幻のシンガーなのである。私がシャンソンに魅了された学生時代、そこにはいつもバルバラやグレコやモンタンのレコードがあった。もちろんそれと同時にジャズやモータウンサウンドのレコードも聴いていた。しばしばクレゴリア聖歌だって聴いていたし、何よりも私の学校でのお努めは礼拝で聖歌を歌うことだった。全て音楽は平等だった。あれは私の青春時代だった。歌は何よりも好きだったが、日本語とラテン語以外で人前で歌ったことなんかなかったし、外国語で歌うことの難しさは知っていたので、まさか洋楽の仕事をしていくとは思ってもみなかった。ところが、シャンソンを日本語で歌う業界があると誰かが教えてくれた。あれは悪魔の囁きだったのか。私の人生が決まってしまったのである。私はこのシャンソ業界に近づくべくトレーニングを始めた。それはほとんど歌の練習ではなく、セリフの練習だった。言葉に対してどう反応するか、それがポイントだった。22才の私にとってそれは結構素敵なトレーニングだった。大人な気分だった。ライヴに行くならむしろ芝居を見た。学生時代欠かせなかったヴォイス・トレーニングは全く止めてフランス詩集を読んでいた。そして苦節何年にして私は件のコンクールに優勝するわ、新人の登竜門と呼ばれた銀巴里のオーディションに合格するわ、シャンソン街道まっしぐらに突き進むはずだった。たちまち大きな矛盾にぶち当たるとも知らずに。(続) 1999年6月 続・パリ祭の季節に思う シャンソンコンクールに優勝すると当時は自動的にこの『パリ祭』に出演させてもらえた。何せそれまで人前で歌を歌うといえば「教会」か「飲み屋」でしか経験のなかった私、まさに天使と悪魔くらいに分裂した私であったので2千人の会場で行なわれる『パリ祭』は大きな魅力だった。会場に入るとそこはもう『芸能界』だった。テレビでよく見る人たちも居たし、なにより挨拶の仕方がかっこよかった。久々に集うスターたちは抱き合ってお互いの無事を祝い(皆様年取ってるから尚更その姿は真に迫った。)映画のセリフみたいな会話を交わしていた。特に芦野宏さんと深緑夏代さんが仲良さそうに腕を組んで歩く姿などはパリの公園みたいだった。そんな中で私は挨拶の仕方が悪いとか、後で色々役に立つお小言を先輩からいただきつつ、その後かれこれ今年で10年夏になるとこのイベントの準備で明け暮れたのである。 シャンソン業界に関わるうち私は重大なことに気がついた。何となくシャンソンという「ジャンル」を歌っていたつもりでいたが、一言で「シャンソン」と言っても様々な流派があるのだった。まずは『レヴュー派』(代表 石井好子)(以下敬称略)宝塚歌劇団出身者にも多いこのタイプはパリのムーランルージュのショーのイメージ。ダチョウの羽根を巻いてステージを歩き回りつつ歌うのが好き。次に『一人芝居派』(代表 美輪明宏)歌に突入する前の導入部つまり前振りが長い。3分間の歌の中で子供が老人になったり、娘が娼婦になったり、男を殺したりするのが好き。さらに『フランス文学映画的ムード派』(代表金子由香利)朗読とも独言ともつかない語りで歌が構成される。しばしば大変哲学的な表現をする。日常生活にもそのスタイルを引き摺る人も多い。そして『現地派』(代表 パトリック・ヌジェ)つまり原語で歌う人達。必ずしもフランス人とは限らずフランスを第二の故郷にしている日本人も多い。フランスに住み時々凱旋公演する人もいる。基本的に何を言っているのかはわからない。最後に忘れてならないのが『カルチャーセンター派』(代表 お金持ちの奥様)この方々が日本のシャンソン業界を支えていると言っても過言ではない。シャンソン歌手の営むシャンソン教室に通い歌を楽しみ、時折豪華な発表コンサートをする。参考のためにプロのステージを見学するので同時に熱心なファンにも変身する。もちろん好きが高じてプロになる人もいる。輪廻転生型。 さて私はどうしたか。この10年であらゆることをやってみた。レヴュー派に挑戦したことすらある。しかし、これぼかりは”ビジュアル”なのである。見てくれの善し悪しで決まると言ってもいい。基本的に「チビ」と「どんくさい奴」は向かない。つまり私がやるべきことではなかった。一人芝居とフランス文学映画が混ざったようなものはどうかと思ってやっていたこともあった。これは結構長い間。ところが、ふとしたことからコーラスやスタジオ録音の仕事が舞い込んできた私はただならぬ大ショックを受けた。つまり、長い間のフランス映画がたたって私はすっかり『音痴』になっていたのだ!!ブツブツ独言を言っている間に『音感』というものが退化してしまっていた。もちろん仕事のレベルとしては使い物にならない有り様だった。大いに慌てた私は歌手という職業に就いていることを深く深く恥じ、同時に反省もした。フランス映画をやるのは止めた。世の中から歌のプロとしての技術を認めて欲しかったからだ。それに私は役者やスターではなかった。技術が無ければただの独語活発な変人にしか過ぎなかった。それでは他にどんな道が残されているのだろうか?今更カルチャーセンターに通っても仕方ない気もしたし、フランス語を使って音楽活動をしていく必然性も感じなかった。私は気づいた。私の居場所はここには無い!!! 次々と矛盾と挫折を繰り返し、ここまでのことに気づくのに10年かかってしまった。何と皮肉なことであろう!竹下ユキの運命やいかに??ところが何ということはない。あっさり問題は解決するのである。いまだに人は私を紹介する時に『シャンソン歌手の竹下ユキさん』と言ったりする。つまりネームバリューが低いので何か肩書きがないと何する人なのかさっぱりわからないからである。しかしこれからは『シャンソン歌手』と呼ばれることを止めればいいのだ。名案である!!しかし、それでは今後何と名乗ろうぞ。『元・シャンソン歌手』というのはどうだろう?よけいややこしい感じがしなくもない。『シャンソン歌手』と呼んで安心されないためにも新しい肩書きが必要だ。あの学生時代、何故フランスのレコードなどを聴いてしまったのか、いや、聴くところまではいいとして何故こんなにもややこしいジャンルと自分の生活を混同したのだろう。まったく人生というものは訳がわからない。こんなことなら変なヒット曲でも作って(例えば『女の胃袋』とか『涙の池袋』とか)一発当てて有名になっておけぱよかった。でもそれだと一生変なヒット曲を歌わなけれぼならない羽目になったろうし、どっちにしたってろくなことはなかったのだろうが・・・。 1999年8月 観客談義 先月、この通信で綾戸智絵さんというヴォーカルについての情報を載せたところ、実に様々な反応をいただいた。是非聴いてみたいと言う人や、さっそく聴いてみましたという人、既に大ファンですという人まで色々だったが、これはやはり綾戸さんが『旬の人』だという証拠でもある。『旬』というのは面白いものだ。その時代の中で、あるいはその人の人生の中で何故か一番力強いオーラを発する時がある。最近ヴォーカルの世界でビックネームを誇っているのは例の「宇多田ヒカル」氏とこの「綾戸智絵」氏であろう。どちらも滅多にない逸材ではあるが、私が何より嬉しく思うのは宇多田氏が緻密な音楽産業のサクセス計画に乗っ取っているのに対し、綾戸氏がライヴハウスから発信しているということである。日本の聴衆もやるじゃない、といった感じがするのである。あるいはもうそろそろ「皆が右向きゃあたしは左」的楽しみの見つけ方を始めているのかもしれない。ちなみについ最近、なかなか入手できない(何故なんだ?)竹下のCDを苦労の末手に入れたという青年に出くわした。ここまで来るとかなりのオタクと見たが、こういう人が居なければ私など一生浮かばれないわけであるし、ヒットチャートの728 番目の曲が一番好きだとか言い出す人がいなければ世の中面白くないわけである。 そこで今月は『聴衆』にターゲットを当ててみようかと思う。いつぞやシャンソン歌手の分類を書いた時も予想以上の反応をいただき「ヘー」と思ったわけだが、中には多少身に覚えがあるらしく、ある箇所で5分間笑ったという人もいた。5分も笑えばかなり健康によろしい。 さて、私はよくヴォ一カル仲間から「ユキちゃんは女のお客さんが多くていいわね。」と言われる。断っておくが、これは「男にもてなくて面倒が無くて羨ましい。」と言われているわけではない。決して。そして確かに私のコンサート(この場合コンサートと言うのは自主的にお客さんを集めて催すノンアルコールに近い音楽会の意味。たとえばジァンジァンみたいな。)は圧倒的に女性客が多い。何故このことを羨ましがられるかというと、そこには奥深い日本社会の仕組みが隠されているからである。 例えば何かエンターテイメントを見に行くとする。ためしに会場に入ったらまず観客のタイプを割り出してみよう。間違って夏休み子供ミュージカルかなんかに行かない限りだいたい観客は大人でそれも女性だということに気づくだろう。もろろん年齢層やたたずまいは様々で舟木一夫だと圧倒的に50代以降の比較的たくましげな女性が多いが、これが宝塚スターになるともう少しお洒落な感じの客席になるとか、話題のミュージカルだと20代が中心になるとかの違いはあるが何にせよ女性である。確かに男性も居るには居るがどうみても妻や彼女につれて来られたという風情だ。男性客が中心という娯楽は競馬や競輪あるいはプロ野球などスポーツ系に偏る。ときにはつぶれそうな寄席に小うるさそうな爺さんがいたりもするが、そういう場所ですら最近は若い女性に席巻されたりしている。どう考えても文化系の催しの会場で働き盛りの背広姿というのは完全小数民族だ。(この小数民族が実は時代のキーを握っているのだがその話はまた後日。) どうも背広姿たちの大半はわざわざコンサートに出かける習慣はないようである。会社帰りにアルコールと女性を求めて酒場へ出没するのは日常茶飯事だし、そこに音楽があったらなおゴキゲンなわけだからライヴシンガーにとっては有り難いお客さんなのだが、この人たちほど当てにならない人種もいない。少しライヴに慣れてくると何時の間にか立派な評論家になり中には新人ヴォ一カルに歌唱指導する人もいる。当然仕事のストレスの八つ当たりもする。私も新人の頃にはすいぶん嫌なお客に会った。中には歌っている間に「こんな歌で何になれると思ってるんだろうね。」私は間奏の間に言ってやった。「少なくともあなたのようにならずに済みます。」最近は私にこんなことを言う人は皆無だ。見るからに恐ろしいからである。それからこういう人はリストラされれば縁が切れる。リタイアすれば家にこもりきる。ここが女性客との大きな違いである。女性には学歴も肩書きも関係ない自由な人が多い。長年応援してもらっているのにその人が何する人なのか全く知らなかったということはしばしばだ。それに女性は子育てが終わると俄然元気になって第二の青春を謳歌する。無駄なことは嫌なので自分の意志で好き嫌いを決めることができる。酒場には行かないが正しいライヴハウスやコンサートには積極的に出かける。ただし男性の名誉のために言っておくが酒場にも紳士は居て我々の頼もしいサポーターになることもある。 兎に角私のコンサートに女性が多いといっても別段不思議はない。極めて一般的な話である。ところがその一般常識を「羨ましい」と言うのはそのシンガーがまだ酒場の外の女性客に出会っていないということを言っているのである。酒場で出会う背広姿を動員してコンサート会場を埋めるなんてこと自体大変な非常事態である。自然の法則に反するくらいだ。それに背広姿は仕事を引き摺るから、中には上司のお気に入りの歌手の応援に駆り出された部下一同が訳も分からず座席を埋めていたりすることもある。聴衆側にも苦労は絶えない。(続) 1999年9月 続・観客談義 いや、びっくりした。とかく自分の知っている範囲が世の中の全てのように考えがちであるが、先日私が訪れたコンサートは見事に私の常識を覆してくれた。前回書いたように、だいたい文化的エンターテイメントの客席は女性客の割合が多い、というのは動かざる事実であるし、出しものによっては球技場で「スポーツ観戦さながら立ち上がったり踊ったりしながらコンサートに参加する若者たち」が居ることぐらい、私だって知っている。ところが私がこの目で見たものは今の今まで一度も見たことのないタイプの観客であった。 出しものはアニメソングを作ったり歌ったりしている40才前後のけして若くない女性ソングライター4人が集まったグループのコンサートで、全曲自分たちで作ったオリジナル、演奏も楽器をあれこれ器用に操りながら皆で分担し歌って見せるのだが、不思議なことに会員おそろいの園児服(としか私には思えなかった。)を着て、おまけに赤ちゃん言葉でしゃべるのである。そのうちのひとりは私の個人的な知り合いで確かに普段から赤ちゃん言葉なのだが、それは彼女の個性なのだと思っていた。ところがその日4人の女たち会員が同じ口調なのでまずはびっくり。しかし柔軟な私は「そういうこともあるだろう」と受けとめ、心を静めた。ぼんやりコンサートを見ているうちにフト不思議なことに気がついた。観客の層はだいたい30才前後。珍しく男性がほとんどだ。そして会場に入る時から気になっていたことだが、ひとりで来ている人が圧倒的である。最後列に座った私は後ろから見る観客の両耳からなにやらイヤホンのようなものが垂れているのを目撃。それもひとりやふたりではない。このコンサートは耳の遠い人たちの集まりなのかと思って注意深く見ると、何と彼らは今目の前で行なわれているコンサートを録音しているではないか?そしてその録音中の音をイヤホンを通じて聴いているのである。この意味がお分かりだろうか?つまりコンサートの音をダイレクトに聴くのではなく、いったん自分の録音機器を通し、それをわざわざイヤホンで聴くという二重の手間をかけているのだ。何故か?さっぱり見当がつかない。 そんなことが目につき始めると、もうコンサートどころではなくあれこれが気になり始めた。となりに座った男は配られていた曲目プログラムに顕微鏡で見なければ読めないような小さな字でいちいち感想を書いている。反対側のとなりの女性はすっかり冷めた一杯の紅茶をちびりちびりとすすりながら、出演者のどうしようもない冗談にいついつまでも肩を揺すって笑っている。そういえば開場してから開演までの約一時間の間、あまり□を開いている人も居らず、ずいぶん静かな会場だなとは思っていた。私のコンサートだったら熟女たちが元気よくしゃべったり「〜さん、ここ空いてるわよ」などと友好的な声掛け運動をしたりして時を過ごすはずなのに。その上アルコールを注文して機嫌よさそうにしている人もほとんど見かけず、じっと一杯のコーヒー紅茶で済ませている人が多い。私はだんだん気味が悪くなってきた。 そうこうしているうちにコンサートは終盤を迎えアンコールタイムになった。全編オリジナルなのでどうせ何を聴いても知らない曲ばかりなのだが、タイトルを言わずに歌い始めたアンコール曲もやはり聴いたことのない曲だった。するととなりの顕微鏡男は私に向かって「今の曲、何て曲だか知ってますか?」と殺気だって聞くのである。ちょっと恐かったが私は「し、知りません。」と本当のことを言った。すると男は「うわあ、残念だ。」と独言を言っている。アンコール曲はプログラムに曲目が載っていなかったのである。「そんなに知りたければ後で楽屋に行って聞けばいいのに。」と私は思ったがその人があまりにひとりで悔しがっているのでそのまま放っておいた。 コンサートが終わり、後から私は知り合いの出演者にその日の不思議な光景について質問した。それに第一コンサート会場で録音を取るなんて禁じられてるんじゃないの?とも聞いた。すると彼女は別段驚きもせず、「あの人たちに録音するな、なんて言ったら二度と来なくなるでしょうね」と言うのだ。彼らはその日自分のご自慢の録音機器で取ったDATなりMDなりの録音物を家で丁寧に編集したり、曲目をラベリングしたりして何年何月何日何処で何を聴き、その何曲目は何という曲だったかを事細かに記憶し、時には人にそれを話すことで大きな満足を得る、というのだ。だいたい、ここでコンサートがあること自体苦労して宣伝したわけではなく、彼らは勝手にインターネットで情報をゲットしてやってくるのだと。大人のアニメファンはこのタイプがほとんどだそうである。だからいつ何処でコンサートをしようとファンは必ず逃さずやってくる。私のように切符売りのオババになる必要もない。アニメの主人公は30才独身の彼らにとってはガールフレンドでもあり、だからアニメのテーマを歌うような女の子はたとえ40を超えていようと、赤ちやん言葉を使うのが正しい。リアルな切符売りのオババなどもっての他である。なるほど、ひとりで紅茶をすすりながら録音機機を仲介に音楽を聴き、曲目を直接質問することもなく悔しがっているのはその辺に理由があるのか。ブキミだ。聞きしに優るオタクたちに遭遇したというわけである。(続) 1999年10月 観客談義・最終回 副題:強化月間とは何か? 人気(ひとけ)と書いて人気(にんき)と読む。こうは見えても取り敢えず私も人気商売をしているわけである。「ひとけ」には殊の外神経質になる。この前のジァンジァンのコンサートは最後の出演ということもあり、皆様には大勢お越しいただいて胸が一杯になるほど嬉しかつた。10年出演してきた場所の最終公演の客席がもしガラガラだったとしたらそれは何かが間違っていたということである。私が悪いか、環境が悪いか。少なくともお客さんはひとつも悪くない。そういう意味で私とジァンジァンは相性よろしく10年間を過ごせたということであった。胸を撫で下ろす思いである。一回毎が真剣勝負であったことは間違いないが、それでも手応えのない時だって長い間にはあった。憎たらしいアンケートももらった。何より自分自身が自信をを失うことも多かった。それでも私を見捨てなかったお客様たちは正に地獄に仏である。お客様は仏様です。私は今心の中でしっかりと手を合わす。ありがとう。ありがとう。 演歌歌手が新宿コマ劇場の一カ月公演の座長を務めることがひとつの歴然としたステイタスになる、というのはよくわかる。以前、友達がバックコーラスをしていた関係上コマ劇場の舟木一夫公演を見に行ったことがある。すごかった。なにしろ一部は時代劇だ。フナキ氏は「おかっぴき」の格好をして悪者退治をする。立ち回る度におばさんファンの黄色い声が飛ぶ。やられそうになると本気で心配する。一カ月間毎日欠かさず見に来る人もいるという。毎日同じ場面で心配したり笑つたりするそうである。もっと驚いたことにわずか30分ほど休憩すると今度は何事も無かったように歌謡ショーが始まりあの玉置弘さんの流れるような名調子の司会と共にきんぴか衣装のフナキ氏が『銭形平次』かなんかを歌いながら出てくる。もう脈絡なんてないのである。その上ファンは歌うフナキ氏に贈り物を渡すためステージに押し寄せていく。フナキ氏も慣れたもので「り〜ふ〜」(どんな意味だ?)などと軽く歌いながら手慣れた手つきで次々とプレゼントを受け取り”プレゼント置場”(ステージの端に設置)にポンポンと置いていく。劇場内は今時珍しい飲食奨励である。そうこうしている間にもアイスクリームや缶ジュースを売りにくる。何だか自由な気分になっていく。私はとても複雑な気持ちになった。これだけの人がフナキ氏に夢中なのである。フナキ氏が羨ましいかと言えば羨ましい気もしたが、じゃあ今度生まれて来るときはフナキ氏になりたいかと言えば絶対嫌だとも思われた。より多くの人に認められたいのは人気商売の真髄だが、どんなかんじで認められたいかはとても難しい。 何にせよ成功はその人が真剣に願うことから始まる。私は何を真剣に願っているのか。いよいよそれに答えを出していかなければならないキャリアに差しかかって来ているのである。コマ劇場でなくていいから、やっぱり自分の歌う場所に無理なく「ひとけ」があることかなあ。来てほしいシーンに「ひとけ」があること。たとえ始めはそのシーンがしっくりこなくても見守ってほしい。必ずいいライヴを提供できるよう努力いたします。というわけで強化月間のライヴハウスに御注目ください。待ってます!! 1999年11月 職業は。 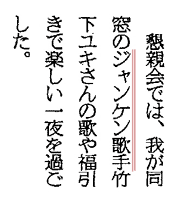 右の記事をご覧いただきたい。これは私の出身校の同窓生からなる、ある地域の会報誌の切り抜き拡大コピーである。私がその会の懇親会にアトラクション要員として歌を歌ったときのことを後日記事にしたものであるが、注目していただきたいのは私の職業である。
右の記事をご覧いただきたい。これは私の出身校の同窓生からなる、ある地域の会報誌の切り抜き拡大コピーである。私がその会の懇親会にアトラクション要員として歌を歌ったときのことを後日記事にしたものであるが、注目していただきたいのは私の職業である。『ジャンケン歌手』とは何か?最も好意的に推測すればシャンソン歌手が語尾変化を起こし、その上その最中にクシャミをしたので濁点が付いてしまったとも考えられるが、一番恐ろしいのは私を本当にジャンケン歌手と思っているのではないかということだ。確かに私の出身校のOBには、世の中の標準と比較すると大幅にずれている人が多い。名前は伏せるが「『鯖』という字は魚偏にブルーでしたっけ?」と言って新聞記者に馬鹿にされたり、「バントだ。バントだ。」とバントの格好をしながらベンチからサインを送ったり、選手に「球がポ〜ンと来たらガ〜ンと打って下さい。」とそのまんまの指導をして笑いものになってしまう人すらいるのだからいわゆるひとつのジャンケン歌手くらいで驚いているようではまだまだ修業が足りないのかもしれない。 それにしてもジャンケン歌手とは何か?颯爽とステージに現れるや否や客席の誰かと一発ジャンケンをし、何でもいいからとにかく歌い、間奏の間には、それどころではないピアニストと無理矢理ジャンケンをし、再び何でもいいから歌い、曲の終わりには会場会体と勝負が付くまでジャンケンをやり遂げる。そういう歌手だと理解するしか他に考えようがない。新しい芸風である。この何年か自分の肩書きを何にしようかと人知れず悩んでいた私であるからして、(シャンソン歌手と名乗るのはシャンソン歌手の現実を考えると気が引けるということが発端であった。)この際、先輩が何かの都合でこう命名してくれたのだから、有り難くこの肩書きで仕事をしていこうかと思う。ただ、いちいち釈明しながら仕事をしなければならないのが少し面倒だが。 橋幸夫は「スイム・スイム」と歌っても「しとしとぴっちゃん」と歌っても「橋幸夫」だったし、美空ひばりは「真赤に燃〜える〜」と歌っても「ひ〜と〜り酒場で〜」と歌っても「美空ひばり」だったことを考えると、歌手が自分の名前を肩書きにできるということはすごいことなのだ。彼らに選曲のジャンルを問い詰めたりするのは間抜けというものだ。演歌を歌おうとジャズを歌おうとあるいはコミックソングを歌おうと「あたしは美空ひばりよ。」で話は終わりりなんである。よ〜し。わたしは誰が何と言おうとジャンケン歌手界の女王になるぞ。勝負はこの右手にあり!!である。 | |||